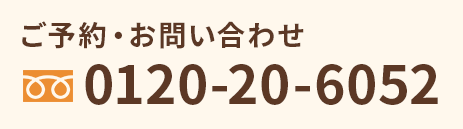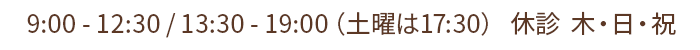「好きな食感」から考える噛む力

日々の食事は、ただ栄養を摂るだけでなく、「お口の健康」や「身体の発達」にも深く関わっています。とくに若い世代にとって、どんな食べ物を好み、どんな食感に慣れているかは、将来の口腔機能や全身の健康に大きく影響を与えます。
日本歯科医師会の調査では、若い世代の多くが「柔らかい食べ物やもちもちとした食感が好き」「硬いものが噛みにくい」と感じている傾向が見られました。特に10代では、「噛んでいると顎が疲れる」といった声も多く、年齢が若いほど噛む力に課題を感じている人が多いようです。
今回は、好きな食感と噛む力の関係についてご紹介します。
食感の好みが噛む力に影響する

柔らかい食べ物は食べやすく、加工食品や時短調理にも合っています。しかし、そればかりになると、噛むための筋肉や顎の発達が十分に促されず、噛む力や歯並び、発音、さらには集中力や姿勢にまで影響を与える可能性があります。
特に子どもの時期に顎をしっかり使わないと、顎の骨の成長が不十分となり、歯並びが悪くなるリスクも高まります。歯が並ぶ「土台」が小さくなるため、永久歯がきれいに並びきらず、矯正治療が必要になることも。
噛む習慣は今からでも身につく
噛む力は、筋トレと同じように使えば育ち、使わなければ衰えるものです。そして、使えば鍛えられるものでもあります。
普段の食事に、繊維質の多い野菜や根菜を取り入れたり、必要以上に柔らかく火を通し過ぎない、小さくカットしすぎないようにするなど、よく噛んで食べる工夫を意識して取り入れてみましょう。
また、「一口30回噛む」ことを意識するだけでも、十分なトレーニングになります。
舌・唇・歯が連携する「食べる力」

噛む力は歯だけでなく、舌や唇、顎など、全体のバランスで成り立っています。噛み応えのある食べ物を噛むことで、これらの機能が連動し、スムーズな食事や正しい飲み込み、発音にも良い影響を与えます。
これらは、食べる楽しさや味わいが深まるだけでなく、将来にわたって「美味しく食べられる」「話しやすい」「誤嚥しにくい」といった、生活の質(QOL)の維持にもつながります。
まとめ
今回は、好きな食感と噛む力の関係についてご紹介しました。
好きな食感は、嗜好の問題だけではなく、お口の発達に深く関係しています。「子どもが柔らかいものばかり食べたがる」「顎が疲れやすい」といったサインを見逃さず、将来の健康のために、家庭でできる“噛む習慣”をぜひ意識してみてください。
当院でも、お子さまの噛む力や口腔機能のチェックを行っていますので、気になる方はぜひご相談ください。
参考
公益社団法人日本歯科医師会 15歳〜79歳の男女10,000人に聞く「歯科医療に関する一般生活者意識調査」
https://www.jda.or.jp/jda/release/cimg/DentalMedicalAwarenessSurvey_R4_11.pdf