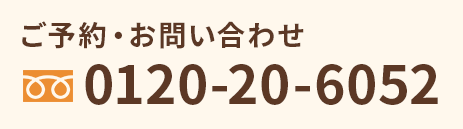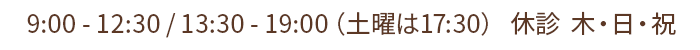歯が溶ける!?「酸蝕症」に注意
みなさんは 酸蝕症(さんしょくしょう) という言葉をご存じですか?酸蝕症とは、飲食物や胃酸などの「酸」によって、歯の表面のエナメル質が少しずつ溶けてしまう状態のことです。
日本人の 約4人に1人 が酸蝕症だといわれており、近年の食生活の変化により増えているお口のトラブルのひとつです。
今回は酸蝕症の原因や症状、予防方法についてご紹介します。
酸蝕症の原因
酸蝕症には大きく分けて2つの原因があります。
外因性
炭酸飲料、スポーツドリンク、柑橘類、酢を多く含む食品など、酸性の強い飲食物をよく口にするなど
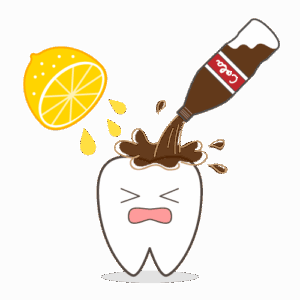
内因性
逆流性食道炎や嘔吐により、胃酸がお口の中に触れるなど

歯が酸に長時間さらされると、表面のエナメル質が少しずつ溶け、弱くなってしまいます。
酸蝕症の症状
初期は見た目や痛みの変化が少ないため、自分では気づきにくいのが特徴です。次のような症状があれば、早めの受診をおすすめします。
- 歯が丸みを帯びてきた
- 前歯の先端が透けたように見える
- 歯の表面がつるつるしてツヤがある
- 冷たい・熱いものがしみやすくなった
- 噛み合わせ部分がすり減っている
- 歯が欠けやすい
- 歯の色が白く濁って見える
- 詰め物や被せ物が外れやすくなった
酸蝕症の予防法

- 間食の回数を減らしたり、酸性の飲食物をダラダラ食べ飲みしないことで、酸にさらされる時間を短くします。
- 酸で柔らかくなった歯のエナメル質を守るために、酸を口にした直後は水で口をすすいで洗い流す。すぐに歯を磨く時も、うがいをしてから歯磨きをするようにしましょう。
- 定期的に歯科検診を受けることで、早期発見・早期対策につながります。
まとめ
今回は酸蝕症の原因や症状、予防方法についてご紹介しました。
酸蝕症は、虫歯と違って細菌が原因ではなく、酸によるダメージで進行します。日常の飲食や生活習慣が関わるため、気づかないうちに悪化することも。気になる症状がある場合は、早めに歯科医院で相談し、生活習慣の見直しと適切なケアを受けましょう。